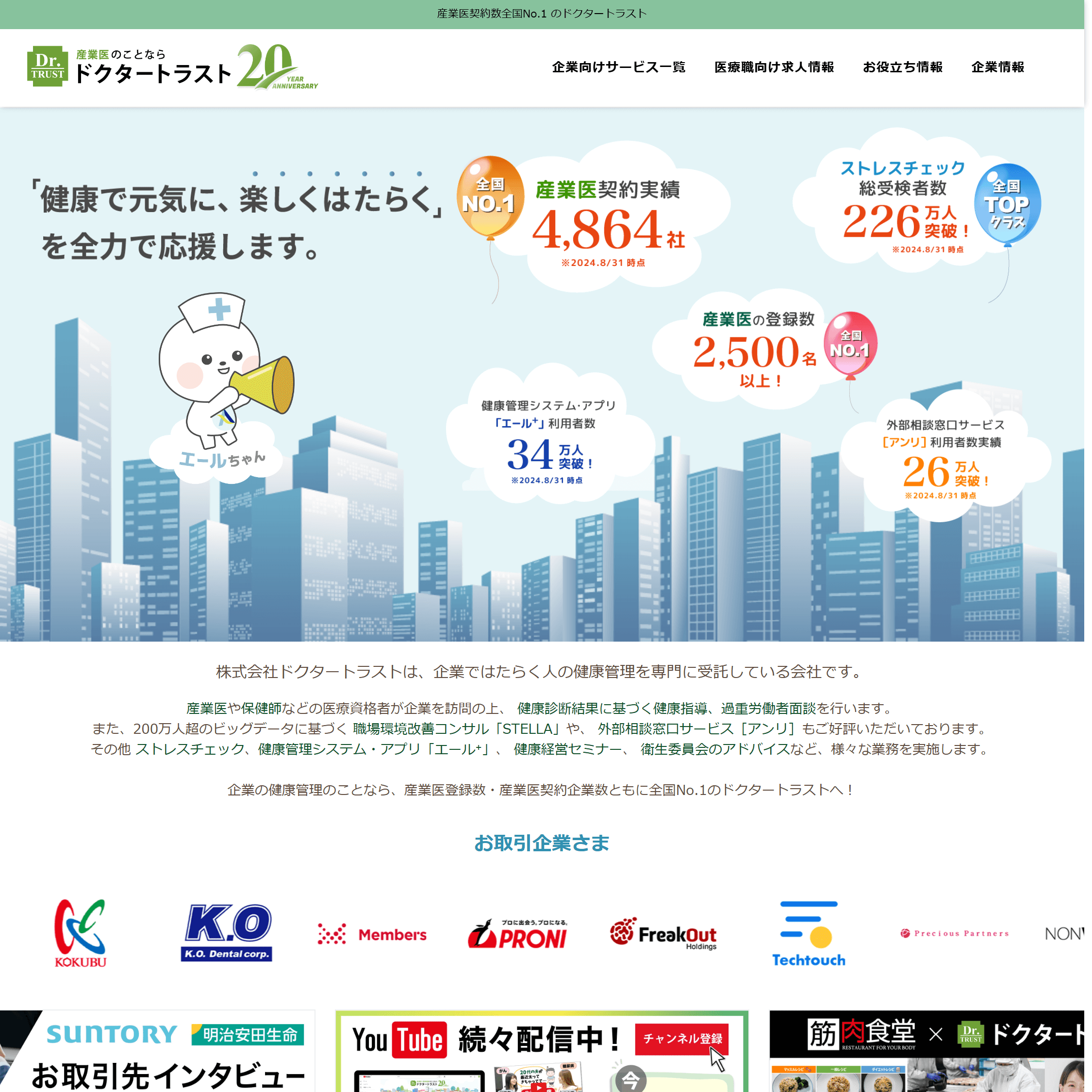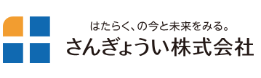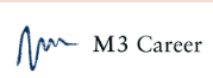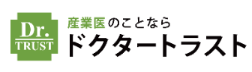「心の健康づくり計画」とは、職場におけるメンタルヘルス対策の中長期的な計画のことです。厚生労働省による「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づいた策定が推奨されています。
企業は従業員の心の健康維持と組織の活力向上のために、セルフケアから職場復帰支援に至るまで一貫した体制を整備することが求められています。今回は計画の目的や策定ポイント、実践方法までをわかりやすく解説します。
CONTENTS
心の健康づくり計画とは?
心の健康づくり計画とは、企業や事業場が策定するメンタルヘルスケア対策の行動計画です。厚生労働省が示す「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づいて策定することが推奨されています。
職場でのメンタルヘルス不調は、個人の働き方だけでなく、組織全体の生産性や安全性にも大きく影響を及ぼします。そのため、企業には計画的・組織的に取り組むことが求められています。
この計画は「心の健康を守る」という理念を具体的な行動に落とし込むもので、セルフケアから職場復帰支援まで一貫して対応できる仕組みを構築することを目的としています。とくに近年は、ストレスチェックの導入や健康経営への関心が高まっており、多くの企業が取り組みを強化しています。
心の健康づくり計画を策定することで、従業員一人ひとりのメンタル不調を予防し、早期発見・再発防止に役立てられます。
メンタルヘルスケアは企業にとって重要な経営課題
メンタルヘルス対策は、従業員の健康を守るだけでなく、企業にとって重要な経営課題のひとつです。心の不調によって長期欠勤や労働生産性の低下が起きれば、業務全体に大きな影響が及びます。さらに、過重労働や職場のストレスが原因で精神疾患を発症した場合、労災認定や損害賠償につながるリスクもあります。
また、ストレスチェックの高ストレス者率や健康診断の有所見者率を改善する取り組みは、健康経営の推進にも貢献します。これにより、健康経営優良法人の取得認定を目指すことができ、企業イメージの向上や人材確保、定着率の向上といった効果も期待できます。そのほかにも、助成金の活用や融資の優遇といった経済的メリットも見込めます。
心の健康づくり計画は、こうしたメンタルヘルス対策の方針や仕組みを明確にするための基盤です。健康経営を推進する企業にとって、欠かせない取り組みと言えるでしょう。
心の健康づくり計画を策定する際のポイント
心の健康づくり計画を効果的に機能させるには、どのように策定するかが重要です。実効性のある計画を作るには、以下のポイントを意識しましょう。
事業者としての方針表明をする
まずは経営層が、心の健康を重視し、積極的に取り組む姿勢を社内外に明示することが大切です。トップの意思表示があることで、従業員や管理職の当事者意識が高まり、組織全体での推進力につながります。
推進体制と役割を決める
次に、産業医、衛生委員会、人事労務担当者など、関係者の役割と連携の仕組みを明確にします。属人化を防ぎ、継続的に取り組める体制づくりが求められます。
また、衛生委員会の位置づけについても、明確に記載します。具体的には、心の健康づくり計画の策定や評価、職場環境改善のための具体的施策を考えるなどの役割を担います。
プライバシーへの配慮をする
心の健康に関する情報は極めてセンシティブなため、個人情報保護を徹底することが重要です。安心して相談・共有できる環境整備もポイントになります。
なお、ストレスチェックや面接指導を拒否したからといって、従業員が不利益を被ることはあってはなりません。プライバシーへの配慮や不当な扱いを受けないことを明文化し、最大限の配慮を心がけましょう。
中長期の目標設定と評価方法を決める
心の健康づくり計画は、前提として中長期的に継続するものです。計画の効果を可視化し、継続的に改善していくためには、数値目標や定期的な評価方法をあらかじめ設定しておくことが大切です。
また、設定する際には具体的な内容を盛り込むことが重要です。「活気のある職場を目指す」といったあいまいな長期目標は評価しづらいため、数値化が可能な目標を設定することが求められます。
4つのケア(階層別対策)を計画に取り入れる
心の健康づくり計画では、厚生労働省が提唱する「4つのケア」をバランスよく取り入れることが基本です。これはメンタルヘルス対策を、個人・管理職・社内体制・外部支援の4層に分けて行う考え方で、それぞれの役割を明確にすることで、効果的かつ継続的な支援が可能となります。
セルフケア
従業員自身がストレスに気づき、対処する力を身につけることがセルフケアの基本です。ストレスチェックを実施することで、自分自身のストレスを意識することができます。
また、社内研修やeラーニングなどで、ストレスマネジメントやメンタル不調の兆候に関する知識を深める機会を設けることも重要です。
ラインによるケア
上司や管理職が部下の変化に気づき、必要に応じてサポートする「ラインによるケア」も欠かせません。管理職向けの研修を通じて、観察力や傾聴力、初期対応のスキルを養うことが求められます。
ストレスチェックの結果を参考にして、従業員の多くがメリットを得られる施策を考えましょう。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医や保健師など社内の専門職による継続的なサポートも重要です。健康診断結果の活用や職場巡視、個別面談を通じて、早期発見と予防に取り組む体制を整えていくことが求められます。
たとえば、従業員が気軽に相談できる窓口を設置することで、面談や保健指導につながる環境を整えることができます。相談窓口の担当者は、職場ごとの課題やニーズに応じて決定します。
事業場外資源によるケア
さらに、産業保健総合支援センターやEAP(外部相談窓口)などの外部機関と連携し、専門的な相談や支援を受けられる体制を整えることも有効です。社内で対応しきれないケースに備えた選択肢を用意することが安心につながります。
とくに、産業医や産業保健師を設置していない小規模企業においては、医療機関・地域産業保健センターなどと連携し、従業員のケアに取り組むことが大切です。
心の健康づくり計画で留意すべき3つの予防ステップ
心の健康づくり計画を立てる際には、3段階のステップを意識することが重要です。それぞれの内容を解説します。
一次予防(職場環境の改善)
一次予防とは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための取り組みです。長時間労働の是正やハラスメント防止、柔軟な働き方の導入といった職場全体の環境改善が中心となります。
また、上司や同僚との良好な人間関係づくりも不調の予防に欠かせません。
二次予防(早期発見・対応)
二次予防は、メンタル不調の兆しにいち早く気づき、適切な対応をとることを目的としています。ストレスチェックの活用や日常的な面談、相談窓口の設置などが代表的な取り組みです。
三次予防(復職支援・再発防止)
三次予防は、休職からの復帰支援・再発防止を目的とした支援です。復職プログラムの整備をはじめとして、職場との連携や段階的な業務復帰など、無理のない支援体制を整えることが大切です。
産業保健スタッフと連携しながら、本人の負担を軽減し、継続的に働ける環境づくりに取り組みましょう。
まとめ
心の健康づくり計画は、企業が従業員のメンタルヘルスを守るために必要な体制と方針を明確にするための基盤です。厚生労働省が定める「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づいた策定が推奨されています。
メンタルヘルスケアを効果的に実施するには、中長期的な計画を立てる必要があります。4つのケアの導入や3つの予防ステップの実践などをバランスよく計画に盛り込むことで、従業員の心の健康維持と職場全体の活性化が期待できます。
また、健康経営やリスクマネジメントの観点からも、心の健康づくりは企業価値を高める重要な取り組みです。継続的な評価・見直しを行いながら、安心して働ける職場環境を築いていきましょう。